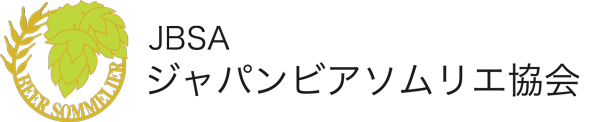2023年、新しい形のビール品評会「Finest Beer Selection by Meininger & Doemens」がドイツで初開催されました。この品評会で90点以上のスコアを獲得した日本とドイツのビールだけを集め、その味わいを楽しめるビアフェスが、シュマッツ松竹スクエア(東銀座)にて、4月6日と7日の2日間開催。
この品評会、何が新しいかと言うと、ビールの優劣を競い合うコンペではなく、品質評価であること。ビアスタイルはあくまでもガイドライン。リミッターがないので、どんなビールでも出品できます。審査はビールごとの個別のスコアシートに従い、香や味わいを分析し、100点満点で評価。世界18か国、約200のブルワリーから880アイテムが出品された中、248アイテムが90点以上を獲得し、ファイネスト・ビア・セレクションに選出されました。上の写真のリンクから、選出された全てのビールとそのスコアを確認できます(ドイツ語、全16ページ)。
審査員はビアジャッジの認定を保有しているだけでなく、ビール業界の中から選ばれた人々です。約60人が一堂に集まり、まずは1日掛けて評点の基準を学ぶ訓練を受け、続く2日間でブラインドテイスティングを行います。そんな厳しい審査を経て90点をクリアしたビールを17種類集めたのが、このフェスティバルです。

前日のプレビューは、このイベントの主催者であるシュマッツカイザーキッチンの創業者で代表取締役のマーク・リュッテン氏(写真右)と、ジャパンビアソムリエ協会理事で国際資格ディプロムビアソムリエのセバスティアン・ホヘンタナ氏による、シュマッツのメルツェンでの乾杯で始まりました。ドイツビールはこの日のために空輸したもので、日本初上陸のビールもあるのでお楽しみに、とリュッテン氏。ビールに詳しくない人でも、ここに来て楽しんで、何が好きか気づいて貰えるきっかけになれば嬉しいとのこと。

ホヘンタナ氏によるファイネスト・ビア・セレクションについての説明に続き、ビアテイスティングの実践解説。外観を見て、香りを嗅いで、口に入れて味わう、という行程はワインや日本酒と同じですが、ビールならではの違いは、泡立ちを見ること。注いでから少し経ったビールはグラスを回して泡を出します。手早く何度も回すと発泡がなくなり味がフラットになるので、ゆっくりと。そうすることで、アロマも出やすくなります。香りを嗅ぐ時は、短くスンスンと。吸ったら呼気は、グラスの外で出し、その後にゆっくり嗅ぎます。

皆で一緒にテイスティングしたビールは、スコア95点で国際ビール部門の第1位に輝いたベアレン醸造所の「シュバルツ」。まずロースト香がして、口あたりはダークチョコレートやカラメル、微かな甘さも感じられます。ミディアムボディで飲みやすく、香りと甘さと苦味のバランスが絶妙。同ブルワリーからは更に「デイ トラッドゴールドピルスナー」が同部門第2位となり、ワンツー独占の快挙でした。両方とも会場で飲めます。

会場には、スコアだけでなく、その味わいがどのように評価されたかを示すレーダーチャートが掲示してあります。自分の感じた印象と照らし合わせながら飲んでみると、新たな発見があるかもしれません。例えば前述のベアレンのシュバルツならこんな感じ。
ちなみに、このビールは、ブルワリー・オブ・ザ・イヤーを獲得したマイゼルスのクラフト系シリーズ、マイゼル&フレンズのチョコレート・ボック。味わいはこのチャートが示すとおりですが、素晴らしさは飲んでみないとわかりませんね。

会場で話題となっていたのが、ケアヴィーダーのアルコールフリーの2アイテム。こちらは、ココナツ・グローヴ・ジューシー・ペール・エール。ピニャコラーダのような味わいですが、レーダーチャートでは、ベリーとホップと松脂の軸が高く振れていて、プロの客観評価と自分の官能評価との比較が楽しくなります。同ブルワリーのドイツ初のノンアルIPA、ü.NNも、モルトとホップと苦味のバランスがそれらしいと、この日の来場者に人気でした。

240405173301225
ラオホ好きの関心を集めそうなのが、クントミュラー醸造所のヴァイエラー・ラオホ。ドイツのラオホではバンベルクにあるシュレンケルラと人気を二分するそうで、スモーキーフレーバーが鋭角的に攻めて来ます。

同じブルワリーのヴァイツェンボックは、ドルンフェルダーの赤ワインに使用した樽で熟成させたもの。濃い赤色を呈するブドウ品種の特性を反映した色味、そしてボディ感があります。ワインの産地としても知られるフランケン地方ならではのコラボです。
日本のブルワリーでは、ベアレンの他、セカンド・ストーリー・エールワークスのジャーマンスタイルのファームハウスエールもヒノ・ブルーイングのサワーバーレーワインなど、普段は飲む機会の少ない希少品もありました。

ファイネスト・ビア・セレクションについての詳細は下のバナーリンクの公式サイトでご覧になれます。